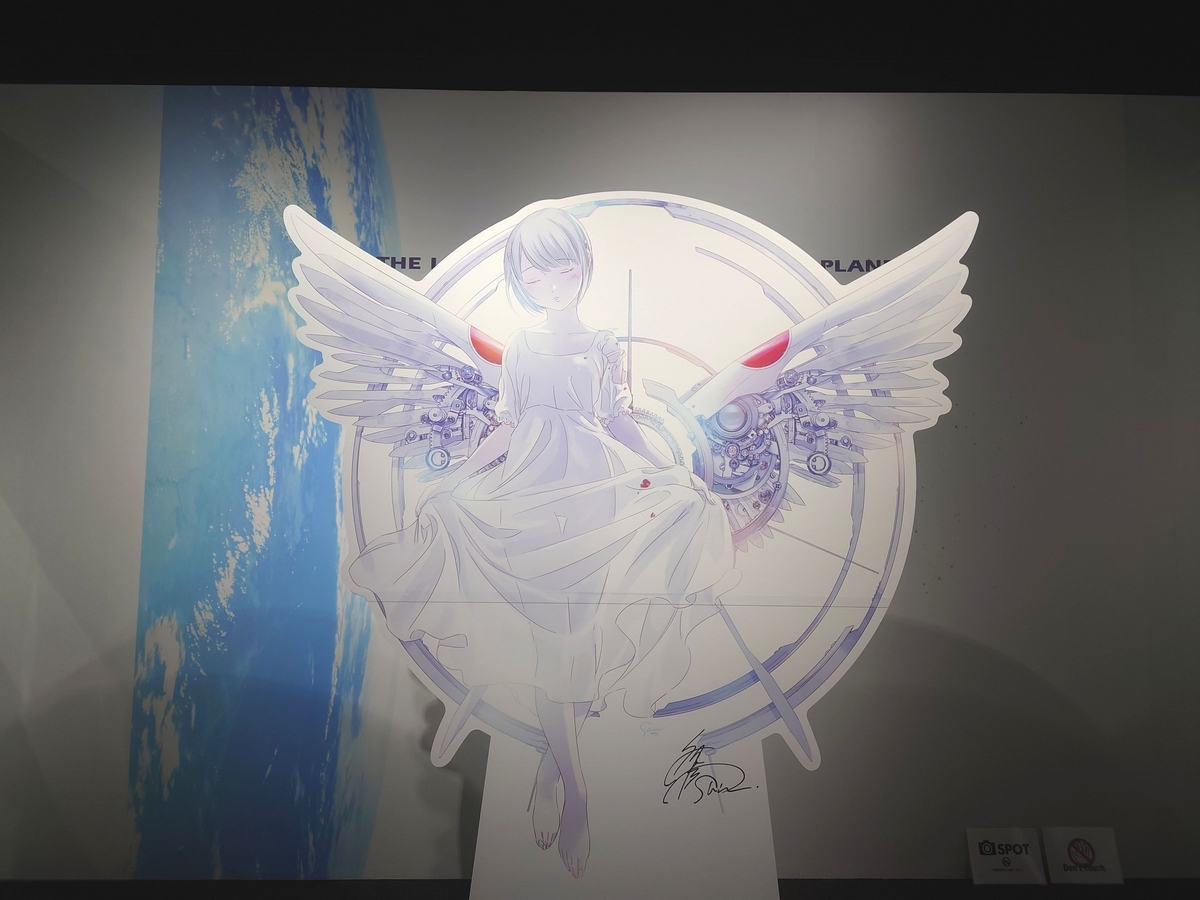映画デデデデが公開されてから、時代に取り残されたこんなブログにもそれなりに人が来て貰えている。うれしい。みんな楽しみだったよな。もしかしたら原作を読んだことのない人が気になって検索してくれたのかも。嬉しい。
筆者もムビチケを前後編セットで購入し、劇場公開を楽しみにしていた。第一話をリアタイで読んだ時から「いいぞいにお!アニメ化ねらえるって!」と失礼千万な応援をしていた。
結構、好評らしい。これもうれしい。
仕事の都合で見に行けたのは初日ではなく土曜だったが、幸運にもネタバレを踏むことなく前章を浴びる事ができた。
そして後章の公開は5月に延期され、しばらく間が空く事になった。
先に言っておくと個人的に前章ではやや不満に思う事があり、それゆえにクオリティアップのため(というが果たして)に延期された後章ではどうか手のひら返しをさせてほしいと思っている。
それもあって、自分のなかのデデデデ前章を見終えた今の時点での感想をきちんとテキスト化して自分の心を落ち着けたいのだ。
ちなみに自分にとってのデデデデは、最終巻のときに書いた記事のこのテキストがそのまま全部って感じだ。
スピリッツで第一話を読んだときから「俺が本当に読みたかった浅野いにおが来た!!!!」と鼻息荒くなったのを覚えている。風刺的なとげを残したエッジの効いた作風が、漫画表現そのものを革新させるようなチャレンジと同居してとてもスタイリッシュだった。主人公の女子高生ふたりの会話はすっとぼけていてナンセンスで、でも空元気のような虚しさも漂っていた。青春の終わりと人類の終わりが同時に忍び寄ってくる……そんなセンチメンタルいにお汁がブシャブシャとあふれ出ていた。そして世界の終幕を目前とした暗澹たる設定。「最終兵器彼女」のアシスタントとしても参加していた事があるという浅野いにおが満を持してド直球のアポカリプス物・セカイ系を描こうと取り組んでくれていた。最高だった。
デッドデッドデーモンズデデデデデストラクションが完結したので - 「正直どうでもいい?」
まだ原作漫画を読んだことのない人は、ちょっとでも映画が良かったと思った人は、漫画も読んでみてほしい。大好きな作品。
・プロモーション
うおおおお幾田りらとあのの共演だああああ!!!!!と朝のエンタメニュースで告知やってたから見てみたらデデデデのことだったから爆笑しちゃった。そんな現代の音楽芸能界のメインストリームがこぞって参加するような作品だったか。そうか。全国200館公開?ギャガ配給なのに?なにがどうなってるの。
エッジーな皮肉も織り交ぜた作品だがしれっと「春休みの王道アニメ映画です」みたいな扱われ方でこの作品が改めて届けられたという事、これは存外うれしいものだった。興行収入的にはどうなってるか分からないけども。
・主役2人の声
良かった、と思う。いや本当。
俺の脳内にずっとあった、俺だけの門出とおんたんはオリジナルボイルスは、もう二度と思いだす事が出来なくなってしまった。ちゃんとハマっていた。
特に門出。やや早口であったり、たまに自信なさげに語尾がすこし下がるようなしぼむようなニュアンスは素晴らしい。映画後半の回想シーンで、無力感と正義にくるっていく過程の切迫感もきちんと演技から感じ取れた。
おんたんは正直だれがどうやっても「なんか違う」「こんなもん」かもしれない。ずいぶんと舌足らずなしゃべり方だと思ったので、それはあえてなのか縁者の特性ゆえなのか。でもふざけていてもローなテンションで入っていく感じ、意外と相手の顔色伺ってる不安げな空気、映画1本見終わるころにはおんたん×あのちゃんは、自分の中でもすっかり完成した。キホ死亡後の道化感と絶叫は見せ所だけあって良かったな。
こんな話題性ありきの糞キャスティングにしやがって、と怒り狂ったpostをしてこわい引リツされてすごすごとpost削除するようなダサいことせずに済んでよかった。
するなそんなこと。
・音楽
主題歌、前知識なしではじめて聞いたけど「絶対ぇTKだ!!!!!」って劇場で叫びだしそうになるくらいTK汁ほとばしる一曲だった。これ前章の空気とは乖離している曲なんだけど、ちゃんとあのエンディングの流れできくとめちゃくちゃワクワクできる。劇場体験としてはかなり良いのでは。
それ以外も劇伴はかなりよかった。円盤が出てきていっきにSFな空気になるんだが、変に盛り上げるのではなく静かに日常の異物感やノイズのような感覚が表現されていた。
後述するがっかりポイントをギリギリで支えていたのは間違いなく音楽の力だった、
・シナリオ
高校卒業までと門出とおんたんの回想シーンで前章は幕を閉じた。
コミックス12巻分をくまなく全部を映像化する事はまぁ無理だろう。原作ファン的にも納得のいく省略と改変だった。
回想シーンはやや唐突感あるし、初見の人からしたらいまこれを見せられる事の意味を掴みづらいのでは?という心配もある。一方で前章のうちからこの世界におけるおんたんの特異性を垣間見せて置くことは、前後編の2章構成としてはスマートな選択だったように思う。メディア展開とは難しいものよ。
・作画
浅野いにお先生のかわいい女の子が動いてる~~~ってだけで◎!!!(あまりにも判断が軽い)
デフォルメきかせた様々なサブキャラクター、ぜんぜん違うタッチのおっさん、みんなが同じ画面に納まって共存しているスマブラ感もデデデデのビジュアル的魅力。アニメーションになることでさらにファニーなかわいらしさが画面全体から感じれた。この幸福感よ。アニメにしてくれてありがとう。
しいて言えば、おんたんの動きはもうちょっとアニメならではの解釈を見せてほしかったな。しゃべってないけど画面の奥で変なことしてるなアイツ……みたいな要素がもっとあってよかった。
・映像表現(演出)
マイナスをつけるとしたらここ。というかここ以外あんまり無い。逆に言えばこのマイナスがでかすぎる。
どういう事かというと特に円盤まわりの描写だ。音楽や効果音によって雰囲気を出していたが、ビジュアル的にはイマイチだったのが正直な所。
原作漫画はマンガ表現としての先進性、とくにタイポグラフィーを駆使した斬新な演出が特徴的だ。スタイリッシュかつスピード感ある表現で、この作品の大きな個性でもあったと思う。

そして日常と同居する圧倒的な違和感を、ビジュアルとして効果的に見せていく。

聞いたこともない音がこの世界では鳴っている。
音のないメディアであるがゆえこの演出がおおきなフックとなる。
世界の異常性をこれでもかと表現し、ビジュアル的にも大インパクトを放つ演出がデデデデで特別好きだった要素だ。かつてこの論点から雑誌に取り上げられたりもしている。
このビジュアルをそのまま映像に落とし込む事は不可能だろう。メディアの違いを理解せよというやつだ。
この映画ではビジュアルではなく音響でその違和感を演出することを選んだように感じる。そしてそれはちゃんと機能して、重要な場面では不気味とも可笑しいとも言い難い、絶妙な音で楽しませてくれた。
ただ、アニメーションとしての表現をもっと探求してくれれば、もっと、もっと自分はこのアニメを愛せたなと思う。
原作の根底にあった「見たことのない表現を見せてやる!!!!」ていうスピリッツが映像から感じられなかった事がショックなんだろうな。フィルムを引き戻していくような演出も原作通りといえばそうだし。
アニメ内で控えめにタイポグラフィ演出で「ぬ」みたいな文字がゆっくり浮かんで消えていく…みたいな描写があって、いや原作要素残すならもっと派手にやれよ!!アニメで違う表現をやるならそれを見せてよ!!!となる。
後章クライマックスに来るであろう地球滅亡のシーンとか、あれやこれや、見たこともない映像をどうか見せてくれ。
あともっと
タイトル「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」ドーン!!!!!
「滅亡まであと●●」ドーーーーン!!!!!
のアホアホデカ文字演出をもっともっとおバカにやってほしかったな。おバカであればあるほど突き放されていくから。無邪気な日常はもう取り返せない、そして未来なんて無いのだと。
ーーー
以上そんな感じ。まぁ書くことは書いたが、やっぱり好きな作品が映像化され劇場でそれを鑑賞できる喜びは大きい。それだけでも満足なのだ。
後章にあたるストーリーは、原作でもとくにビジュアル的に実験的かつ破滅的な仕掛けが多く施されており、映像化のハードルはとても高いと思う。頼む。頼む。後章をどうか、最高の滅亡を、どうか。